お盆の新習慣「お盆玉」とは?
お盆になると実家に帰省し、久々におじいちゃん・おばあちゃんに会うお孫さんもいます。
そこでお孫さんがもらうかもしれないのが「お盆玉」です。
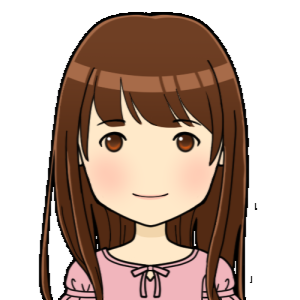
「お盆玉」とは?

お盆というと社会人にとっての夏休み、子供にとったら両親の実家に行って、普段なかなか会えない祖父母に会う機会でもあります。
そんなお盆ですが、最近、新習慣として「お盆玉」というものが出来ました。
「お盆玉」とは何なのでしょうか?
「お盆玉」とはお盆にもらうお小遣いのことです。
つまり、「お盆玉」とは、お正月でいうお年玉のことですね。
お盆は遠く離れた親族に会うことも多く、久々にあったおばあちゃん・おじいちゃんはお孫さんが可愛くて仕方ありません。
そのため、何かプレゼントやお小遣いをくれます。
これがお盆玉です。
確かに久々に会えるお孫さんには、誕生日やクリスマスなどに会えない分、何かあげたいと思ってしまう気持ち、わかります。
祖父母にとってお孫さんは大抵の場合、目に入れても痛くないほど可愛い存在です。
しかも、ご家庭によってはお正月に会えないというご家庭もあるでしょう。
すると、1年に数回しか会えない時にお小遣いをあげたいと思うのは仕方ありません。
数年前まであまり聞かない名前でしたが、実はお盆玉の歴史は古く、つい最近できたものではありません。
では、いつぐらいからあるものなのでしょうか?
実は昔からあった?
実は「お盆玉」とは江戸時代からある風習です。
当時、商家には丁稚と言われる奉公人がいました。
丁稚は住み込みで働くため、普段はなかなか実家には帰れませんでした。
しかし、お盆やお正月には帰ることを許されており、その時、お盆にもらったのが「お盆玉」という小遣いです。
当時は現金というより、下駄などのモノを与えるのが普通でしたが、時代と共に徐々に変化し、昭和初期には現金を手渡すようになったそうです。
そして奉公人に挙げていたものが、今では久々に会うお孫さんや甥っ子、姪っ子にあげるモノへと変わっていきました。
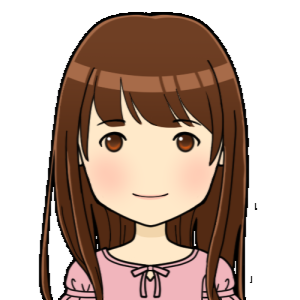
お盆玉の相場は?現金でなくてもアリ?
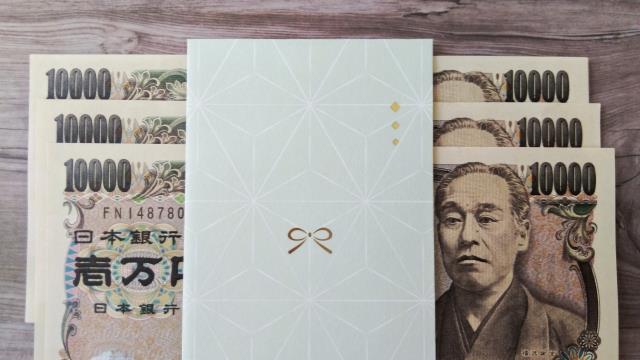
では、「お盆玉」とはやはり現金がいいのでしょうか?
その場合の相場はいくらぐらいなのでしょうか?
まず、「お盆玉」とは昭和初期にはモノから現金に変わっていったと前述しましたがが、現在の「お盆玉」とはどんなものが喜ばれるのでしょうか?
厳密に決まりはありません。
そもそも、お盆玉をあげるかあげないかは自由です。
ですから、モノをあげるか、現金をあげるかというのも自由なのです。
小さなお子さんにお盆玉をあげる場合は、ついつい子供が喜びそうなおもちゃやお洋服を買ってあげることもあるでしょう。
幼稚園・保育園にあがるぐらいの年齢のお子さんならおもちゃでもいいかもしれません。
しかし、それ以降になると、おもちゃを選ぶのはちょっと難しくなってしまいます。
というのも、お子さんの好みがあったり、すでに持っている場合があるからです。
あらかじめ、お子さんが好きなキャラクターや欲しがっているものを知っているなら、そういったおもちゃを買ってあげるのもいいかもしれませんが、久々に会うお子さんの好みがわからないというのであれば、おもちゃはちょっとハードルが高いかもしれません。
そして、そんな時に便利なのが現金です。
現金なら、親御さんに渡せば、後からお孫さんや姪っ子・甥っ子が好きなものを買ってあげられます。
また、小学生高学年以上になると、自分でお小遣いを貯めて好きなモノを買ったり、友達と遊びに行った際に使ったりするので、現金の方がありがたいかもしれませんね。
また、商品券やQUOカードといった形もありますが、使える場所が限られてしまう場合もあります。
小さいお子さんの親御さんとしても現金の方がありがたいかもしれません。
というのも、帰省先でもらった場合、それを持って帰らなくてはいけないからです。
おもちゃをいただけるのは嬉しいですが、大きめのおもちゃだったりすると荷物が増えてしまいますからね。
その点、現金なら今後必要になりそうな衣類や子供のための日用品を買い揃えられます。
まあ、どういった形であれ、もらえるのは嬉しいですね。
「お盆玉」の相場は?
では、「お盆玉」とはお盆の「お年玉」みたいなものですが、現金の場合、相場はどれくらいなのでしょうか?
現金を渡すとしても、いくらぐらいがいいのかなかなかわかりませんよね。
そこで相場を調べてみると、3000円から1万円程度です。
大抵、小学生ぐらいの子には数千円、高校生には1万円といった感じで、年齢によって金額が上がります。
ただ、いくら渡すかはご家庭によって異なるので、いくら渡してもいいです。
中には入学祝いや卒業祝いを渡せなかった分、多めに渡すというのもいいですし、頻繁に会ってお小遣いも度々渡しているので少なめに渡すのもOKです。
現在、お盆玉をもらっているのは?
では、「お盆玉」とは新しい習慣になりつつあるといっても、世間ではどれくらいの人たちがもらったり、あげたりしているのでしょうか。
現在、お盆玉の習慣がある人は40%ほどのようです。
そして、その多くが現金派ということです。
確かに久々に会うお孫さんや甥っ子・姪っ子さんの好みは分かりづらいですからね。
おもちゃや本というよりも現金で渡す方が、好きなものに使ってもらえていいのかもしれません。
ちなみに、お年玉を渡す時の定番といえばポチ袋ですが、お盆シーズンになると「お盆玉」と書かれたポチ袋も販売されています。
つまり、「お盆玉」はじわじわと浸透しつつあるようです。
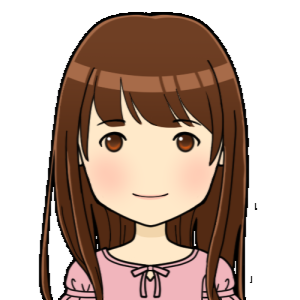
お盆の新習慣「お盆玉」とは?まとめ
お盆玉とは昔からあるお盆にお小遣いを渡す習慣ですが、ここ最近、さらに世間に浸透しつつあるようです。
コロナ禍ということもあり、なかなかお孫さんや甥っ子、姪っ子に会えない人も多いでしょう。
だからこそ、今度会った時にはお小遣いでも渡そうという気持ちが大きくなるのかもしれませんね。

